【新刊】ムスリムが取引で利息と不確実性を忌避する理由
経済
2025.02.19
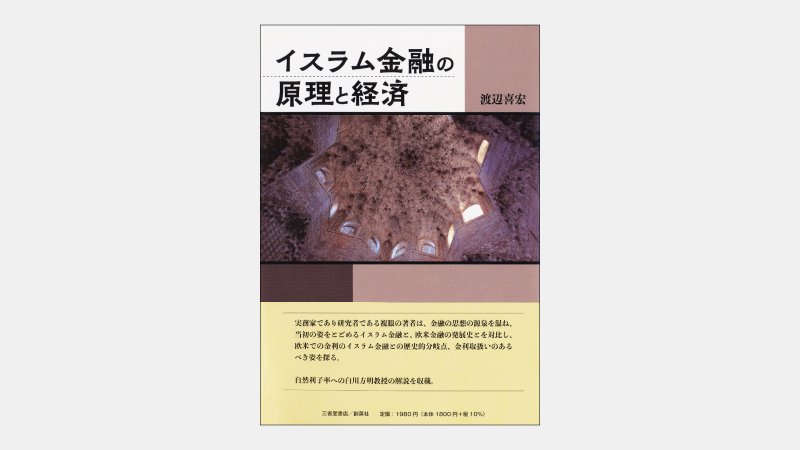
『イスラム金融の原理と経済』
渡辺 喜宏 著 | 三省堂書店/創英社 | 202p | 1,980円(税込)
1.イスラム金融と貨幣・金利と利潤
2.投資とイスラム金融
3.イスラム金融の禁止項目 Gharar
4.イスラム金融とTime Value of Money
5.伝統金融の危機とイスラム金融
6.イスラム金融とイスラム経済
巻末寄稿 ゼロ金利について思うこと―政策金利、市場金利、中立金利―
白川方明 青山学院大学特別招聘教授(元日本銀行総裁)
【イントロダクション】
湾岸の産油国をはじめとするイスラム教国家では、神の言葉や神の使徒であるムハンマドの言行が、国民の生活習慣のみならず、政治・経済を導く原理となっている。
とくに、独特なのが「イスラム金融」だ。「金利」をとることを厳しく禁じることがよく知られるが、その本質は、欧米で主流の金融の考え方とは大きく異なるようだ。
本書では、イスラム金融の原理を、欧米を中心に現代まで続く伝統的な金融とその歴史などと比較しながら、詳しく解説している。
イスラム金融は、神の下ですべての人は神の召使いであり、代理人でもあるため平等という前提のもと、riba(金利)、gharar(不確実性)、maisir(賭博)などを禁じ、衡平で公正な取引を行うことに大きな特徴がある。商取引はすべからく実需と結びつくものとし、マネーがマネーを生むような金融取引とは根本的に異なるのだという。
著者は、和歌山大学経済研究科客員教授、公益財団中東調査会評議員。旧東京三菱銀行アジア本部長兼マレーシア現地銀行会長、同行専務取締役グローバルコーポレート部門長などを歴任した。
新規会員登録(無料)をすると本ダイジェストの続きをご覧いただけます。(2025年2月27日まで)会員登録はこちらから
既にSERENDIP会員の方は本ダイジェスト全文を下記から閲覧いただけます。
法人の会員はこちら
個人の会員はこちら