【新書】日本が「仕事をしないロボット」で先行する理由
テクノロジー
2025.03.18
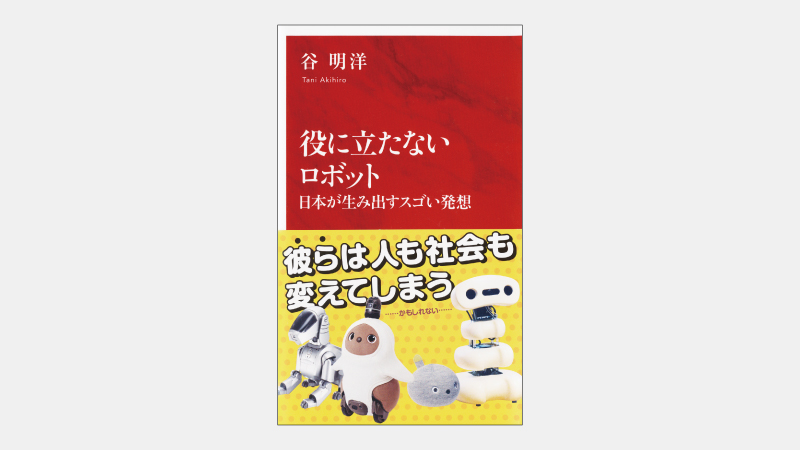
『役に立たないロボット』
-日本が生み出すスゴい発想
谷 明洋 著 | 集英社インターナショナル(インターナショナル新書) | 272p | 1,045円(税込)
1.どのような「役に立たないロボット」が存在するのか?
2.「弱いロボット」はウェルビーイングを引き出す
3.「LOVOT」、人を幸せにするテクノロジーのあり方
4.「ヘボコン」、笑いの奥に潜むもの
5.「AIBO」供養に見る「壊れる」価値
6.人や社会を拡張するロボットたち
7.「役に立たないロボット」は本当に役に立たないのか?
【イントロダクション】
従来の人間が担うタスクを肩代わりしたり、補助したりするAIや、AIを搭載したロボットの進化はめざましく、その開発に世界中の研究者が鎬を削っている。
その一方で、とくに何らかの「作業」をこなすわけでもないが「癒し」を与えるコミュニケーション・ロボットが、日本を中心につくられ、受け入れられている。
本書では、工場の産業ロボットや家庭用お掃除ロボットのような「役に立つロボット」とは異なる、仕事をしない、あるいは仕事ができないロボットについて、現場での取材をもとに考察。
対象となるのは、犬型ペットロボットの「AIBO(アイボ)」やアザラシ型セラピーロボット「PARO(パロ)」、家族型ロボット「LOVOT(らぼっと)」といった実機があるものだけでなく、漫画やアニメに登場するロボットキャラクターを含む。それらの本当の価値、なぜ日本で受け入れられているかなどを、本書では分析している。
著者は科学コミュニケーター、静岡新聞記者、日本科学未来館勤務などを経て、睡眠ウェルネスアドバイザーや、地域を旅する「さとのば大学」専任講師など、多岐にわたって活躍中。
新規会員登録(無料)をすると本ダイジェストの続きをご覧いただけます。(2025年3月26日まで)会員登録はこちらから
既にSERENDIP会員の方は本ダイジェスト全文を下記から閲覧いただけます。
法人の会員はこちら
個人の会員はこちら